
↑こちらは「Canvaで生成」というプロンプトで生成された画像です
画像というものは
撮影でもなく
作成でもなく
生成する時代です
個人的には近い将来「撮る」という動作がなくなり
「カメラ」というガジェットもなくなってしまうんじゃないかとさえ思います
さて、みなさんすでにご存知かと思いますが
CanvaのAI生成機能が先日アップデートされました

メニュー名とUIが変わった感じですね…
そもそも
無料版では機能制限が多くなりすぎてしまい
テンプレに至っては有料ラインナップが過半数を占めています
ちなみに無料ユーザーは生成の際もクレジットによる制限(月/500クレジット)があります
一回の生成で画像は4点作成されますが同じプロンプトで再生成にも1クレジット消費します
AI生成を利用する際には注意してください
ということで
クレジットを使い込んで生成機能を使ってみました
先日とあるバラエティ番組内で
「有名な歌謡曲のタイトルでAIに画像生成させるとどんな画像になるのか?」
というお題で生成された画像からタイトルを当てるというクイズをやっていたので
アップデートされた「ドリームラボ(元マジック生成)」を使い同じお題でやってみました
※参照画像・設定などは使わずにプロンプトに曲名だけを入力し生成しました

↑「ギザギザハートの子守唄」 チェッカーズ
モチーフとしてのハートですが空間の歪みとして表現されてます
ギザギザ感もどこにいったのか抑え気味で子守唄が省かれた様な感じです
寓話的な雰囲気が子守唄の連想でしょうか
不完全な分もう少しプロンプトを増やせば劇的に変わりそうです

↑「情熱のバラ」 THE BLUE HEARTS
情熱的ではなく幻想的というか幻惑的な雰囲気になりました
描写に関してはAIの感性は外国寄りなのかなと思います
これの使い道が全く思いつきませんが
油絵のような色彩の重厚感は圧巻です
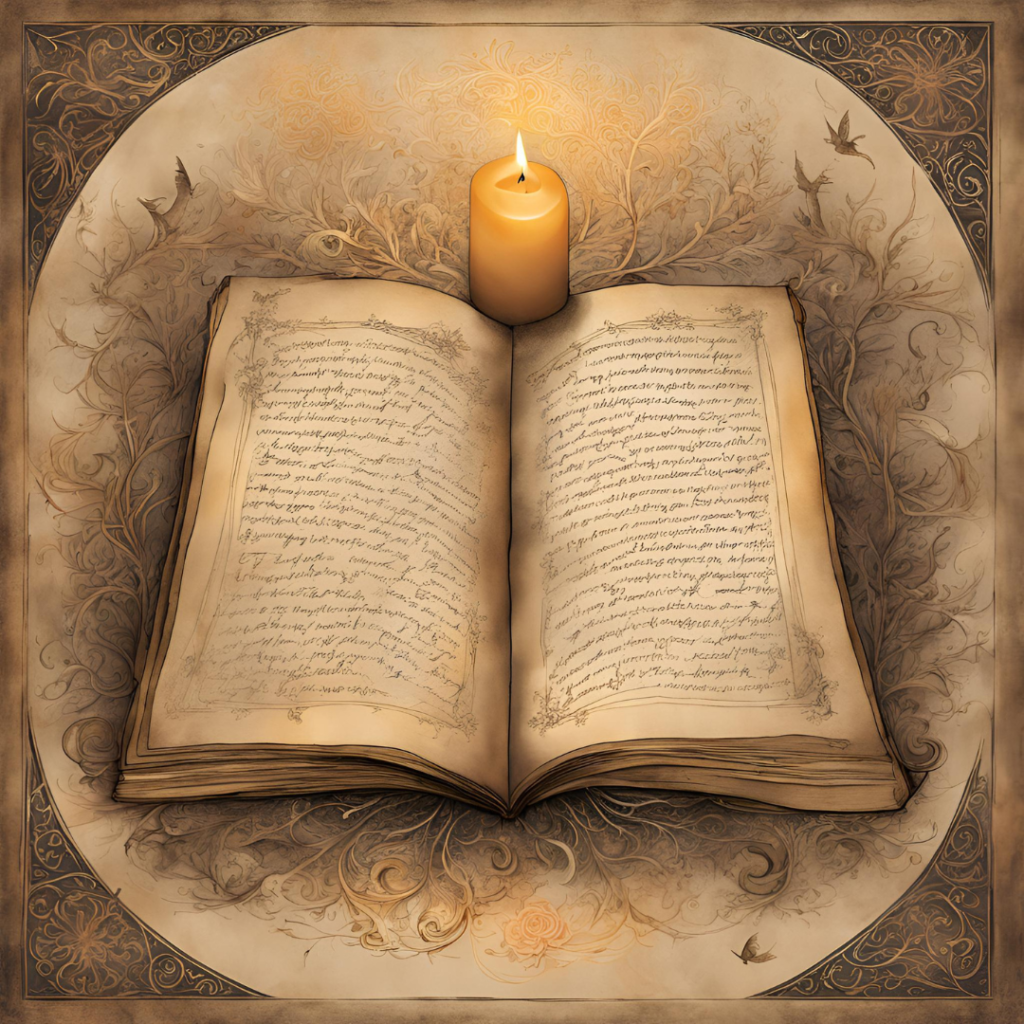
↑「名もなき詩」 Mr.Children
中世がベースのSFファンタジーな世界観
詩=書物でしょうか
繊細かつ緻密に描かれた本や模様などは圧巻ですが
この画像や雰囲気からタイトルの連想は難しいですね

↑「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」 B’z
曲のタイトル同様に画像も理解が難しいものになりました
繊細かつ圧倒的な描写と表現力です
やはり人の手の表現がうまくできないところが残念
ある意味これがAI生成された作品の特徴ともいえます
一枚の絵としてはインパクトが強烈です

↑「ルージュの伝言」 松任谷由実
情報量が少なかったせいもあって
なぜか外国のアニメ風で獣耳キャラに解釈をされました
「伝言」もイマイチ表現できていません
シーンや人物描写はかなりハイレベルですが
やはり手がぐにゃぐにゃで正確に描ききれていませんね

↑「いとしのエリー」 サザンオールスターズ
幻想的な雰囲気が繊細なタッチで描かれていますが
不完全というか未完成の感じがします
「いとし」の解釈が難しかったのかもしれません
複数の人物が一体化しつつぐにゃぐにゃ
悪夢のような描写になってしまいました
いびつな世界観ですが実際にCDのジャケットにありそうなビジュアルです

↑「怪獣の花唄」 Vaundy
花に囲まれて怪獣(モンスター)が叫んでますね
こういうディティールのキャラクターは生成で登場しがちです
実際に今まで何度かイラレなどで生成したことがあります
花の描写や配色、アングルにはセンスを感じます
やってみた中で曲名のイメージに一番近い仕上がりでした

↑「僕の背中には羽根がある」KinKi Kids
遠近感が曖昧です
この羽根は着脱可能?
それにしても、羽根の質感が凄まじいです
ちなみに「僕」なのに女性的な人物描写
ジェンダーレスなイメージなのでしょうか
この様に
画像のAI生成は情報ソースや使うアプリケーション、
生成時の設定などによって出来栄えに振り幅が大きく
こういう短いプロンプトで表現するケースでは
ひたすらトライアンドエラーの繰り返しになります
概ね意に沿わないものばかり生成されます
なので、毎回「なんだこれ?」という感じです
こちらの慣れもありますが
この手のAIは日毎に学習しUI等も改善されていくので
いずれはもっと良いものを簡単にアウトプットできる様になるのでしょう
しかし、
現時点でもAIの生成速度や表現力には驚かされます
数秒で生成される複数枚の画像
全面にわたって緻密で繊細な描写
中にはとてもこの世のものとは思えない
良くいえばサルバドール・ダリの絵画作品のような
空間は歪み得体の知れない物体が度々創造されるので
AIの底知れぬ闇を垣間見れた気がします…
まだ実作業では画像そのものを生成するより
部分的な加工や修正などがメインの用途になっています
しかし、一つのツールとしての存在意義は確立しているため
各種アプリケーションにおいての普及速度はかなり早いと感じています
まずは使ってみて
さらに用途の幅を広げていければと思います
↑記事を見たり、いいねと思ったら、ハートマークを押してください